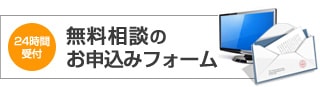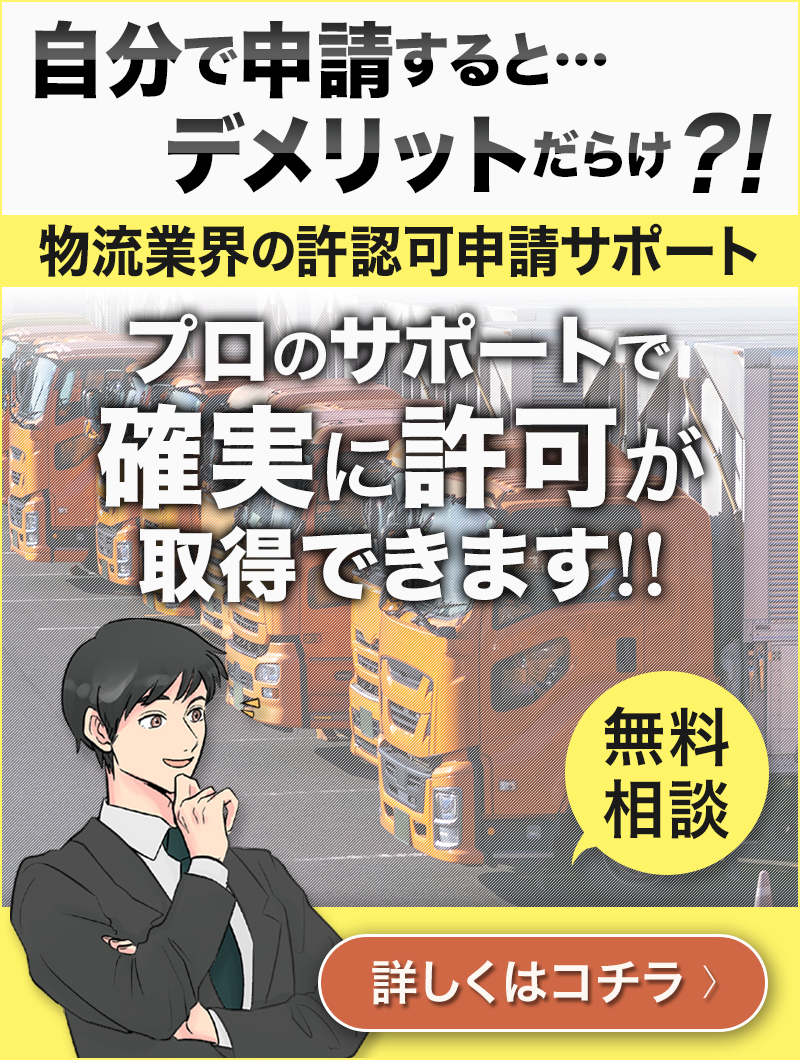特定貨物自動車運送事業許可の取得要件を詳しく解説

運送業を行うには、貨物自動車運送事業許可が必要になります。
では、特定貨物自動車運送事業許可をもらうにはどのような要件が必要でしょうか。
1.特定貨物自動車運送事業許可の要件
貨物自動車運送事業には、「一般貨物自動車運送事業」と「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」の3つの事業があります。
トラックを使用して単一特定の荷主から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合が、「特定貨物自動車運送事業」です。
特定貨物自動車運送事業許可のための要件は、以前と異なり、一般貨物と同じになりました。そのため、許可のためには以下の人的要件、物的要件、財産的要件の3つの要件をそれぞれ満たすことが必要になります。
【人的要件】
①申請者や会社の役員が欠格要件に該当しないこと
欠格事由とは以下の事由になります。
|
1.1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない 2.一般/特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない 3.申請者が法人の場合、その親会社や実質支配会社などが 2 に該当する 4.一般/特定貨物自動車運送事業の許可取消し処分に係る聴聞の通知を受けて、処分決定までの間に事業廃止の届出をした場合、その届出から5年経過していない 5.一般/特定貨物自動車運送事業に関する立入検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業廃止の届出をした場合、その届出から5年経過していない 6.上記 4 の事業廃止の届出をした法人の役員であった場合、その届出から5年経過していない 7.未成年者の場合で、法定代理人が1~6(3除く)および8に該当する 8.申請者が法人の場合、役員が1~7(3除く)に該当する |
②運送事業に専従する常勤の役員うち1名が法令試験に合格すること
特定貨物自動車運送事業に専従する常勤の役員(個人の場合、申請者本人)が、許可申請後に行われる法令試験に合格必要な有資格者を配置することが必要になります。
1回目に不合格でも再試験が受験できます。2回目も不合格だと許可申請は却下処分となります(若しくは申請取下げを申し出る)。この試験は奇数月のみに行われるので、不合格になってしまうと次の試験まで待たなくてはならなくなる結果、許可をもらう予定が2カ月遅れになってしまいます。
③必要な有資格者を配置すること
営業所ごとに、定められた人数の「運行管理者」、「整備管理者」を配置しなければなりません。運行管理者は、営業所ごとに、保有車両29両までは1名以上、以降30両ごとに追加1名を選任、配置する必要があります。
整備管理者は次のいずれかに該当する者でなければなりません。
|
1.整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者 2.1級、2級または3級の自動車整備士技能検定に合格した者 |
④必要な人数の運転者を選任すること
営業所ごとに使用権限を有する車両を5両以上有し、運転者も5名以上必要になります。
また、自動車検査証の用途は「貨物」となっていることが必要です。
【物的要件】
①営業所があること
建物が都市計画法、建築基準法、農地法、消防法等の法令に抵触していない営業所が必要です。
また、営業所として適切な規模(目安としておよそ10㎡程度以上)があり、借入の場合は2年以上の使用権限を有することも必要です。
②休憩・睡眠施設があること
睡眠を与える必要がある場合は、1人あたり2.5㎡の広さを有することが必要です。借入の場合は2年以上の使用権限があることが必要です。
③営業所に併設または一定の距離内に、全車両が収容できる車庫があること
営業所に併設することが原則ですが、併設できない場合は一定の距離内(例:東京都特別区内、横浜市、川崎市に営業所を設置する場合は20㎞以内、埼玉県では10㎞以内)に、一定の間隔を取って全車両が収容できる車庫を置く必要があります。
④必要な数の車両数があること
営業所ごとに、運行に必要な車両を5台以上確保することが必要です。
【財産的要件】
①所要資金
所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が次により算定した所要資金に相当する金額以上であること等資金計画が適切であることが求められます。
例えば、人件費・燃料費・油脂費・修繕費の6ヶ月分の運転資金、自動車重量税、自動車税、保険料各1年分を所要資金として算出します。
②所要資金の常時確保
所要資金の全額以上が、申請日以降常時確保されていることが必要です。
「常時確保」として、預貯金の「残高証明」を2回提出します。
1回目は、許可申請時に提出します。2回目は、許可処分前に提出をします。
③損害賠償能力
100両以下の自動車で事業を行う場合は、「対人無制限・対物200万円以上」の任意保険に加入する必要があります。
危険物の輸送などを行う場合は、さらに必要な賠償金額を担保できる保険に加入することが求められます。
2.まとめ
特定貨物軽自動車運送事業は改定され、ハードルは高くなっているので、慎重な計画の策定が必要です。
申請の際にはご自身だけで判断せず、貨物軽自動車運送事業に詳しい行政書士に相談するようにしましょう。